就職で出た大阪から地元和歌山に戻り、自分の書いた曲をバンドにアレンジして演奏する生活。
そんな中でふつふつと湧いてきた「デビューしたい!プロになりたい!」という思い。
俺らならイケる!
そして東京進出。
が、スムーズにデビューできるわけでもなく、バイト三昧・ライブ三昧で食っていくのに必死……念願の、CDデビューを果たします!
けれど、業界の渦に飲まれていく…
そんな中、師匠と呼べる人に出会います。それは、今につながる一番のターニングポイント。
会社を興してもらい音楽クリエイターとしてだけでなく、経営者としてのビジネススキルを叩き込まれました。
でも、ある事がきっかけでバンドを解散。会社をたたみ、また地元に戻ります。
阿部:家業を継ぐことに対して、親御さんだったり社長ご自身は葛藤のようなものはなかったのですか?
親は親で「サラリーマンになれ」って言いましたよ。
言いましたけど、僕は地元に戻って、家業を継いだとは言ってるんですけど、
実は、半年間引きこもりになったんです。
外に出ないんです。夜中になったら友達に連れ出してもらって、朝帰ってきたら夕方まで寝てる。そんな生活ですね。
あれが多分、人生最初で最後の引きこもりですね。
阿部:では、その引きこもりから家業を継ぐようになったきっかけはあるんですか?
あります。
子どもができたことですね。
継いでいくというより、子どもを食わしていかなきゃならないんで。
それが一番ですね。
阿部:それはサラリーマンではなかったんですね。
そうですね。それは親も間違ったアドバイスはしていなくて、うちって7代続いてますけど、それだけで食っていける規模感とかレベルではやってなかったんですよね、うちの親父の時までは。
だからうちの母親は、ずっと看護師を正職員でやってたわけです。
それは僕もわかってたんですけど、親父の代までは
「農業にしても漁業にしても、その前の先輩から引き継いだものを何も変革させないでやってるから食われへん」
って思ってたんですね、僕は。
要は経営努力。

「時代も変わってるわけやから、そんな200年も続いてるやり方そのままやっても、そら食われへんやろ」と思ってたんで。
あとは、僕自身のキャリアも変なキャリアで、一般企業には必要とされないスキルなんで。
サラリーマンでギリギリ食えるかどうかのところより、自分の努力でね、売上も収益もあげれる。ベースは家業として農業漁業があると。
だからここを自分の考えで改革をしたり拡張したりして、この事業で普通に人並み以上に食えるようにしよう!と決めて継いだんです。
阿部:では、家業を継がれてすぐに「変える」という挑戦をされたのですか?
そうですね。まず変革と規模拡張を同時にやりました。
紀州南高梅というのはブランドになって50年近いので、ある程度収益をあげて裕福に梅農家さんが食っていけるシステムができあがっていたわけです。
ただ、あまりにもうちが代々受け継いできた農園の面積が小さかった。
システムはもうこの地域でできあがっているので、まず、農園の規模感を10倍くらいにしょうと思ってやったんです。
阿部:みなべ町役場には、世界で一つだけの『うめ課』があると伺いました。みなべ町はどんなところなんですか?
みなべ町っていうのは農家さんだけでなく、梅に依存して成り立ってる町なんです。
みなべ町の人口って7,000人くらいなんですよ。
でもね、その7〜8,000人の中の大げさじゃなくて5,000人くらいは、何かしら梅に関わる仕事に従事してます。
たかだか、そんな人口7〜8,000人の町にですね、梅干しを加工するメーカーさんが100社ありますから。
梅農家だけで1,000軒はありますからね。
だからもう、梅がコケたらコケる町です。
阿部:長年続いていってるということは梅で成り立つということですよね?
そうですね。そのシステムを先人の方々が築き上げてきたからですね。
要はね、全国の梅干しの生産量のマーケットシェアの70%がみなべ町と隣接する田辺市なんです。
だから梅で成り立つ町になっています。
阿部:そのみなべ町の中で社長が農家として目を向けられたのは、面積を広げることだったんですね。
そうです。まずは梅農家として栽培面積を広げようとしました。
ただ、栽培面積を広げるのって、作物なので苗木を植えたからってすぐに実が収穫できるかってそうじゃないんですよね。
3年とか5年とか最低かかるわけですよ。
じゃあ、広げてからその広げた分がちゃんとリターンとして返ってくるのって、3年から5年後なんですよ。
「その3年から5年の間何をするかな」
ってなった時に僕は、漁業に目を向けたんです。
漁業っていうのは、改革をしました。
それまでの代々使っていた船や装備を一切やめて、最先端の設備を積んだ2周りくらい大きな船に乗り換えました。
ハイテク、ハイテク、ハイテクで。

僕自身ずっと漁に関しては、子どもの頃からじいちゃんや親父に連れて行かれてたんで、色んな事は頭に全部入ってるんですね。

魚が捕れるか捕れへんかは、勘やとか生まれ持った素質やとか
漁師の世界ってそんななんですよ。
だけど絶対に科学的なものがあると思って。
それを自分が沖に行きながら、潮だとか何だとかデータを集めて、ハイテク機器を駆使しながら
「このパターンでここにこういう風に仕掛けると必ず捕れるよね」
ということを、3年くらいかけて確立するんです。
僕元々、漁師は好きだったんでね。
子どもの頃から行ってたというのもあるし、自分がやってみても「儲かるとか儲からないではなく、好きか嫌いかでいくと漁業は大好き」なんで。
ただやっぱり悲しいかな、改革をしたことで、漁獲量は他の漁師と違って安定的に大量に捕るようになるんですけど…
結局ね、梅はもうブランドになってシステムが出来上がってるんですけど、そういうブランドになっていない農産物や漁師が捕ってくる海産物って、自分で値段を決めれないんですよ。
浜値というのがあって、入札とかで買いはるから、仕入れた後、利益をのっけて売らないといけないから安いんですよね。漁師の取り分としては。
たくさん捕ってくるんだけれども単価が安い。
だから、大した儲けにならないんです。
生活はそんなに楽にならないわけですよね。
かと言って、まだ3年から5年経つわけでもないから、梅の方の収益があがるわけでもない。
「どないしょうかな」
と思ってた頃に、仲卸を始めます。
地元は独特で、梅農家さんが1次加工した梅干しを、町に100社くらいある製造メーカーさんに間をつなぐ「仲卸、仲買」という特殊な職業が成り立ってる地域なんです。
紀州南高梅というのは意図的に開発された梅なんで、自家受粉ができない。
だから、豊作不作の乱高下がすごく激しいんです。
製造メーカーさんは一番何が困るかって言うと、不作で原料が手に入らなければ商品が作れない。
そうすると、商社との安定供給の契約を巻いているので、莫大な違約金をとられちゃうんですよ。
だから不作年は必死で原料を集める。
僕が関わったその年がその「不作年」
幼馴染で製造メーカーの娘さんと結婚した彼がいて、
そのメーカーが原料に枯渇している。
このままだと数千万の違約金を商社から求められてしまう。
「なんとか梅農家の横の繋がりで、原料を集めてもらえないか」と頼まれます。
その彼は実はバンドの時の仲間。
東京に音楽をやろうと3人で出ていって2ヶ月で和歌山に戻ったのはそいつなんです。
戻ったのにも理由があって、その彼は僕らと東京に出ていった頃には1歳の娘がいたんでね。その娘と奥さんを捨てて出てたんですよ。
その彼とここでつながるわけです。
彼から「原料を集めてもらえないか」ということでまわりに声をかけて回ったら、めちゃめちゃ集まったんです。
そうしたら、そのメーカーの社長が
「君ら才能あるから、やりーよ」
「うち全部原料仕入れさせてもらったら、うちとしても安定するから、農業や漁業やりながら副業でやったらどうや」
そんな声をかけてくれたんです。
でも、その時はたまたま一発目でビギナーズラックやったんですけど、仲卸も難しい世界でね。
その後は、3年間くらい苦労したんです。
農家さんから買うわけですよね、梅を。
それをメーカーさんに売るんですね。
やっぱり、新人は農家さんに信用がないわけですよ。
だから、売ってくれないんです。
それで、なかなか集まらなくて。
同業で僕らよりも先にやってるベテランは信頼があるので。
信用がなくて売ってもらえない僕らは、開店休業状態。
3年くらいはそれで、のらりくらりとやってたんですけど、4年目か5年目に幼馴染と2人で
「今から1年間だけ、ほんまに、本気でこの仲卸の仕事にウエイトを置いてみやへんか」
って話になったんです。
「1年やってあかんかったら、俺らにはこのジャンルの才能ないわ」
それで、お互いやってる家業を絞って、1年だけ仲卸業に専念したんです。
それが1年後、実を結んだんです。
どかーん!といったんですよ!
平成24年くらいだったかな、と思います。
阿部:そこから一気に波に乗られたんですか?
そうですね。でもまだ法人をつくろうとは思ってなかったんです。
そこから4年くらいは面白い程儲かったんで、
欲しいもんは何でも買える。
もう笑いが止まらん状態です!
家も建てれたし。
子どものことも心配いらん。
色んなところが整っていきます。
4年間くらいはそんな状態だったんですけど、
実は僕、仲卸をやりながらずっと感じてたんですけどね。
仲卸というのはもう40〜50年くらい続いてますけど、
「この業種はずっと存在し続ける業種じゃないな」
っていうのは途中で思ってたんです。
必ず梅の業界から、仲卸が必要じゃなくなって、これじゃ生業を立てられない時代が来るというのはずっと思ってて。
ちょうど平成28,29年あたりですね。
どうしよう。
今やったら資金もある。
でも、梅かぁ…梅だけではなぁ…
そう思ってたちょうどその時、目に入ったのが、元安倍総理大臣がマニフェストで出された
「6次産業推進」
要は、農業者漁業者が自分で加工をやって販売までやる。
1次2次、3次掛けるの6次産業化。
それが推進された時に、うちは農業も漁業もやってるから、2次と3次をやればいいんだなと思ってました。
色んな補助金もたくさん出てたんです。
「これええかもな」って思って「会社を作ろうかどうしようか」と迷ってた時。
その頃はお金もあって定期的に東京に行くようにもなってたんですね。
行く度に弟(現、紀乃屋の専務)に会ってました。
弟はその頃IT大手企業に就職中。
yahooの下請けで激務すぎて二度程倒れてですね。
そういったこともあって
「もし兄貴が法人作って起業すんねんやったら、俺も一緒にやるわ」
「よし、わかった。6次産業を柱にまず会社を作る」
3次産業の部分が販売なので、他の6次産業者っていうのは地域の「みちの駅」に卸したり「産直市場」に卸したりがスタート。
「うちはお前(弟)がITで、Eコマースできるからインターネット販売のところを3次でするで」
1次は、拡張したものが農業も漁業もある。
後は加工の工場作れば6次産業いけるよ。
「ほな会社作ろう」
そう言って作ったのが、紀乃屋です。


6次産業は、このままもっと成長させていきたいと思っていますし、色んな施策をとってる中で、違った形での出会いではありましたけれども、オアシス倶楽部さんにも一翼を担っていただけて非常に光栄だと思います。
阿部:ありがとうございます。こういった関わりを持たせていただけて有り難いことだと思っています。では社長、法人化された紀乃屋さんの『理念』を聞かせていただけますでしょうか。

コーポレートサイトでも謳っているように、
やはり自分で振り返った時に、人生45年経ちましてね。
物心ついた頃から色々その時々、人間なので変わりますよね、価値観とかね。
でも、その中で自分が自分の人生振り返った時に、
「変わってないことってなんやろう」
って思ったんですよね、このコンセプトを考える時に。
それが所謂、世にないものであったり
または自分を中心として、自分が主役として見た時に、
「自分やったら、これは作り変えた方がええよね」
「ただ、これはまわりの人は古いだのダサい言うけど、これ無くしちゃったら人間の歴史の中でえらい歪になるよね」
という両極端な思いを、常に僕は、子どもなりに小さい世界観の中から今に至るまで、ずっと自問自答してきたなと思ったんです。
それが一番
これを掲げよう。
僕の人生の中で『不変』
要は、変わってないところってそこやな
そう思ったんですね。
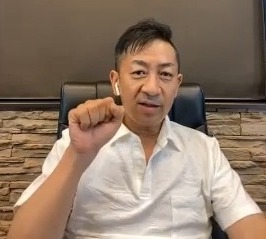
だから、後付けで考えたとか、大人になって考えたとかっていうよりも、
自分の人生振り返ったら、そこだけが自分の一貫性やったなと思ってて。
それに気づいたっていうことですね。
先はどうとかっていうのはもちろん考えてますし、6次産業だけに限らず、今自分が立ち上げた事業もこういう風に発展させたい、大きくさせたいビジョンとかね。そういうものは描いてるんですけれども、
やっぱり僕って思うのは、
世の中とか人の歴史って、すごい長いじゃないですか。
自分がたかだか生きれる60年から80年くらいのものって、一瞬なんですよ。
どれだけ自分がこうあってほしい、
100年後がこうあってほしいとか、
自分がいなくなってからこうなってほしいとか思っても
それは僕、儚いもんやと思ってるんですよ。
その理念を洗脳してしまった人間が後継者になったら、それはそれで、そこへ付いていく社員は、僕は不幸せになると思ってるんで。
やっぱりその時その時の時代を先入観のない人がね、
その時の鋭い感性で感じて切り取って、切り開いていってつないでいく。
それのずっと連鎖やと思うんですよ、人類の歴史というのは。
だから、諸行無常感が僕はすごい好きで。
でもね、結局人は、一時の栄華の為に本気で一生懸命頑張るんです、みんな。
だってすごい美味しいディナー食べたい、
めちゃめちゃ高いディナー食べたいっていって頑張るじゃないですか。
でも食べるのは、一時で一瞬で。
変な話、そんなもの死んじゃえば関係ないし。
だけどそこに人っていうのは、一瞬一瞬に一生懸命いくじゃないですか。
その連続の連鎖で繋がってるものだけだと思ってるんですね。
とは言え、先の無常観っていうのは自分でもわかってるわけ。
わかりやすく言うと、
誰かが打ち立てた「これは誰にも破られないであろう」記録も、絶対いつか後輩たちに破られるわけですよね。
でも、わかりながらでも、人生捧げてそのアスリートはやるわけじゃないですか。
僕もそういう考えなんで。
ただ、生きた証というか、もがいた証を、
悪い意味で先入観持たせたり、影響は持たせたくないんですけども、
たった一片、ひとひらでもいいので
あぁこれって、あいつの片鱗だよねと。
見せたい。

それが最先端の伝統になるっていう。
100年後2、00年後に見たら、
これ当たり前で便利なものが続いてるよね、いいよねって言われるものを、
当時の人達が遡った時に「僕だった」
っていうのが何か一つあればいい。
ささいな事でいい。
阿部:ありがとうございます。社長のその思いに今胸がドキドキしています。いいお話を聞かせていただきました。
それでは社長、今回オアシス倶楽部では利休園さんの商品もご紹介させていただきました。
利休園を事業継承されたことや利休園への思いを聞かせていただけますでしょうか。

元々は今回、田坂社長と僕をつないでくれた、現利休園の取締役をやっていただいている徳田さんという方がいらっしゃって。
まさにこの方が、利休園とも縁をつないでいただいた方なんですけども、
前経営者がビジネス的に行き詰まってて悩みがあると相談を聞いたところ、インターネット販売がこれからの時代どうしても必須になってくると。
ただご自身にそのノウハウもなければ、社員にそのスキルをもってる人間もいない。
そういうことで、紀乃屋さんのITに協力いただきたい。
要は、インターネット販売の代理運営をやってくれないかという、当初は業務提携のお話だったんですね。
まず業務提携をして、その後すぐにまた相談があるということでお話を聞くと、
利休園さんって、うちとは違って400年というすさまじい歴史があってですね。

大手の商社の取引口座をもっていて、取引先がすごいわけですよね。社歴も長いし。
ただちょうど東京オリンピックの前年くらいだったんですけども、国内の食品衛生基準に対する声が高まりましてね。
グローバルに見ると今もそうですけど、まだ日本って先進国の中でも欧米に比べると食品衛生の基準が低いんですよね。
HACCP、ISO、FFFCっていう風なグローバルに耐えうる基準を取得した。
または、それに耐えうる仕様で作られた製造工場で作られていないと、取り扱いしませんよ。
というのを東京オリンピックの1年くらい前から、大手さんが取引先にアナウンスしてたんです。そこで京都利休園さんも言われたわけです。
老舗で古いということは、工場も建物も古いわけですよね。
ってことは、とてもじゃないけどHACCP、ISO仕様ではありません。
ただそれを建て替えて、また1から工場を作るっていうことはとても無理。
そういうことで、前社長から相談を受けました。
またその前社長も利休園を継ぎたくて継いだ方ではなかったんです。
前々社長が実は、利休園歴代の中で一番大きくした方なんですけども、その方が社長の時に前社長は社員で工場長という立場だったんですね。
その前々社長が九州に商談出張に行って、出張先でそのまま亡くなったんですよ。心筋梗塞かなにかでね。
誰が継ぐかという話になった時に、その前々社長っていうのはすごくやり手で、凄すぎたんで、みんなそんなすごいカリスマの後を継ぎたくないわけです。
というところで、前社長は
「自分のことを拾いあげて、職人から工場長まで育ててくれた恩」のある社長が亡くなった。
でも、このまま誰も継がなければ、この会社はなくなる。
という事で継がはったんです。
だから経営は大嫌いだし、経営がやりたくて継いだわけではない状態だったんですよ。
どっちかっていうと、この利休園というのを託せるというか任せたいと思える人が現れれば譲ろうとずっと思ってたらしくて、その製造工場の話をいただいた時に、うちの和歌山の本社にちょうどISO、HACCP仕様の工場を建設してる時だったんで
「じゃあ中澤さん(前社長)うちの工場ができたら、利休園の商品をうちの工場で作ったらいいじゃないですか。製造で下請けしますわ」
そんな話をしてその後、中澤社長に言われたのが
「もしよければ、利休園を引き継いでもらえないか」と。
そんな事を言われて、僕も専務も考えました。
社歴も長すぎて背景がすごいんで、いきなりM&Aやって事業承継で名義変えるのは不安なんで「1年間、僕らを取締役に入れてもらって、一緒に1年間させてもらえませんか」と提案しました。
1年間一緒に共同経営をして、ある程度のことを把握できて
「これやったら継げる」と思ったのと
やっぱり中澤社長の思いとか代々の社長の考え
プラスね、これ僕が一番「継げる」って思ったのは、
お茶の世界のシステムというか、仕来り、スキーム、ロジックですね。
それと梅の世界がすごく似てたんです、僕の中ではね。
だったら、扱う商品がお茶と梅で違うだけで、農家が栽培してそれを仲卸で仕入れてという業界の仕組みが同じだな。
これやったら、自分がもってるノウハウそのまま、ほぼほぼ横展で使えるなと。
それとね、それはほんまの事ですけど
カッコええ方の理由で
自分の欲望だけでいくと…
京都にね、入りたいなって。
僕実は、農業漁業をやってた時代に一度、紀州の産物を京都のど真ん中で売ってもらおうと思って京都に入っていこうとしたことがあるんですね。参入しようと。
でもね、見事に弾かれて。
だからそれで「あっ!京都の会社を手に入れたら内側や」と思って。
「やりたい事がやれるな!」って思いました。
阿部:すごい!その京都に参入しようとしたのはいつ頃のお話ですか?
東京から戻ってきて農業漁業を本気でやり始めるじゃないですか。
やり始めて仲卸の話をもらう少し前くらいですね。
結局、漁業で漁獲量を増やしても単価がダメ。
農業の規模を増やしても収穫量が増えるまでにもう少し年数がかかる。
じゃあ、今自分が栽培して作ってるものや海で捕ってくるものを少しでも1個あたりの単価を高く売れば収益があがるなと思って色々僕なりに調べたのと、
僕どうしても『京都』っていうのが頭にあってですね。
「京の都のど真ん中で売ってやろう」
そう思って行きました。
でも弾かれた。
『京都に出る』っていう『欲望』が下心ですね。

阿部:では社長、最後に京都利休園の今後と社長の利休園への思いをお聞かせいただけますか。
紀乃屋も利休園もそうですけど、農産物や海産物のブランドって全国色んなところにブランディングがあるじゃないですか。
僕が海外の関係の事業をしている中で、色んな海外の人の声を聞いた時に
グローバルっていう視点で見ると、やっぱりね『京の都』『古都京都』っていうブランディングは違うらしいんです。
それに、今の日本の現状を見ても、国内のシェア争奪に参戦するよりも、もっと視点を広げた方がいいんじゃないかと。
コロナも落ち着いてきましたし、グルーバルな展開にアプローチを今、一生懸命かけています。
例えば国内やったら、中村藤吉さんや伊藤久右衛門さん福寿園、伊右衛門さんはネームあるよね。
日本ではそこの方がネームがあっても、じゃあ東南アジアやアメリカに行った時に、
「京都利休園の方がネームあるよね」
っていう状態にしたいですね。
「世界の利休園になりたい」




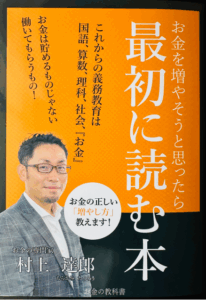
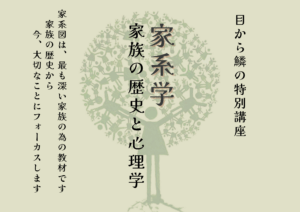
![投稿についてもっと詳しく アグリカルチャー農業男子奮闘記[Takumi&タカ男]](https://relife-consulting.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1993-300x300.jpg)